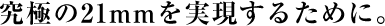レンズを設計するにあたり、クリアすべきポイントは3つあった。
1)超広角レンズらしからぬ周辺性能
2)ディストーションの抑制
3)オートフォーカスの性能アップ
デジタルカメラ全般に言えることだが、美しい画像を得るためには、レンズを通過してきた光に角度をつけず、できる限りまっすぐにセンサーへ当てるのが理想だ。これは画像周辺部の発色や結像に大きく影響する。特にFoveonというセンサーは構造上、この点に敏感だった。世の中にはたくさんのカメラ用レンズがあるが、実は基本となるレンズ構成のパターンというものが存在する。その多くは古くからあるものだが、中でも超広角レンズには、光に角度をつけて撮像面に当てるレンズ構成が多い。これには2つの理由がある。一つは角度をつける方が設計が簡単だったこと。もう一つは感材がまだフィルムだった頃は、そこに当たる光の角度に寛容だったことだ。つまり光に角度がついているのが当たり前であり、またそれで何の問題もなかったのだ。しかし今はそうは行かない。
レンズというものの性質上、光を完全にまっすぐにすることは不可能。ではどのぐらいの角度なら良いのか。設計チームがまずやったことは、Foveonセンサーに角度をつけて光を当てた場合の許容値を調べることだった。光の角度を0.1度刻みで変えていき、得られたデータを検証する日々。その結果、鏡胴はボディとのバランスがとれるぎりぎりまで長いものとなった。原理としては物理的な全長を稼ぐことで、レンズの前面から入った光を何枚ものレンズを通過させながらゆっくりと曲げていき、光がレンズの反対側から出る時点で無理なくまっすぐにする仕組みだ。これで満足できる結果を得ることができた。
長い鏡胴は、ディストーションを抑えることにも有利に働いた。鏡胴に余裕があるぶんレンズ設計の自由度が広がり、取り入れたいアイディアをいくつも試すことが出来た。さらに、レンズの材料となる硝材や、加工技術の発達がそれを後押しした。「0」には最終的に8群11枚というレンズ構成が採用されたが、そこにはシグマ独自の特殊低分散ガラスであるFLDガラスが4枚、同じくSLDガラスが2枚、また大口径両面非球面レンズと片面非球面レンズが各1枚ずつ使用されている。「10年前だったら到底不可能だった」と幸野は言う。試行錯誤の連続ではあったが、蓋を開けてみればディストーション率0.5%以下という目標を達成していた。
オートフォーカスについても進歩があった。dp1からdp3までは、ピントを合わせる時にレンズの前玉を繰り出す方式を採用した。しかしこの方式は可動部分の質量が大きくなる。重いものは動かす時にも、また止める時にも大きな力が必要になり、フォーカスの精度とスピードの低下につながる。「0」で採用したのはインナーフォーカス、つまり鏡胴内にあるレンズを動かしてピントを合わせる方式だが、ここで動くレンズは1枚だけとした。これなら質量が小さいぶん、正確に、素早く動かすことができる。これも鏡胴内に十分なスペースが生まれたことで可能になった技術だ。またレンズを動かすステッピングモーターには1000分の15mm単位で動かせるものを使った。測距のアルゴリズムも一新した。被写界深度が深い超広角レンズといえども、「真のピント」は確実に存在する。そのピントを探し出して初めて、Foveonセンサーの高い解像力を100%生かすことができる。
こうして幸野の言う「素性のよいレンズ」は出来上がり、「0」を世に出す準備が整った。コードネーム「0」は「dp0 Quattro」という正式名称を与えられ、いよいよ生産段階に入った。